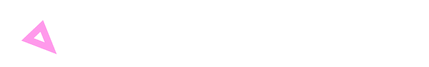子どもを教育する塾において、教師と生徒の関係はどうあるべきなのでしょうか。そして、親はどういう風に関わればいいのでしょう。迷っている方も多いと思います。さらに、入試の状況も毎年変わってきています。不安になるのももっともです。こうした問いにキチンとした答えがある、つまり教育の哲学があってこそ、子どもを目標に導けると信じています。
1. 中学受験のための新しい教育理念
1-1.記憶について考えてみる。
学習するとは、ある意味、記憶することだと言えます。まずは、記憶について考えてみましょう。
記憶には短期記憶と長期記憶とがあり、長期記憶されるのは短期記憶されたもののごく一部だと考えられています。できるだけ早く多くのことを忘れないと、不要な過去の情報が、刻々と変化していく状況に臨機応変に対応するのを妨げるからでしょう。
有名なエビングハウスの実験によれば、忘却の速度に個人差はありません。だとすれば、いかに不要な情報を忘却し、必要な情報だけを記憶するかという意識的もしくは無意識的な工夫が学力の差を生むのだと考えられます。
まずは、長期記憶のためには、どのような学習法が有効なのかを考えてみましょう。
第1に、長期記憶のためには、一夜漬けは逆効果であり、毎晩、少しずつ記憶すべきです。大量の情報を一度に無理矢理詰め込むと、忘却が早まることがわかっています。また、人は、夢を見ている間に、記憶を整理していると考えられています。
第2に、長期記憶のためには、初めて習ったことは1か月以内に繰り返し復習すべきです。エビングハウスが示したように、記憶を保つには、繰り返し復習することが効果的です。また、脳は、新しい情報を1か月かけて整理し、必要なものだけを長期保存すると考えられています。
第3に、長期記憶のためには、テスト(もしくは問題演習)→間違え直し→テスト(もしくは問題演習)…というサイクルが効率的です。以下の実験のように、インプットよりアウトプットの方が忘却を防ぐようです。
| テストの復習 | 追試 | 1週間後の再テスト | |
| A | すべて | すべて | 約80点 |
| B | 間違えたもののみ | すべて | 約80点 |
| C | すべて | 間違えたもののみ | 約35点 |
| D | 間違えたもののみ | 間違えたもののみ | 約35点 |
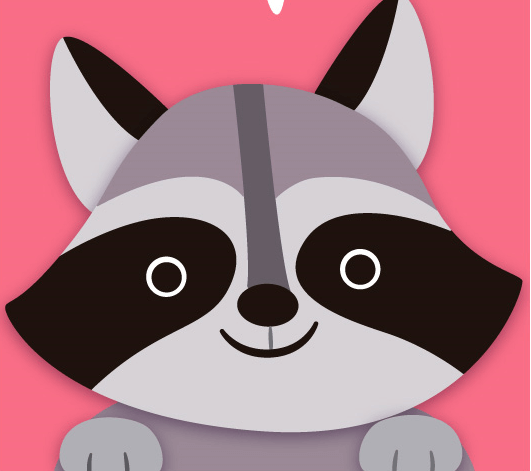 あみこく
あみこく
1-2.知識の関連付けで記憶する。
しかし、以上のような単純暗記のみを学習だと考えることはできません。
ベルを鳴らしてから犬にエサを与えることを繰り返すと、ベルを鳴らしただけで犬が唾液を出すようになるという実験がかつてパブロフによってなされたことがあります。このように、繰り返しと「エサ」(または「ムチ」)によって学習効果を高めるという立場があります。
しかし、人間は、パブロフの犬とは異なり、新たな知識を記憶するとき、それを既有知識の体系にとりこもうとするか、既有知識の体系を変化させてそれをとりこもうとします。なぜなら、断片的な知識より、相互に関連付けられた知識の方が記憶に残りやすいからです。だとすれば、学力の差は学習の量だけではなく、学習の質、つまり、知識が相互に関連付けられて記憶されているかどうかによっても生じると言えます。
後者の考え方はいくつかの点で示唆的です。
1つには、記憶だけでなく、問題を解くことも知識の関連付けだと考えられるからです。当然ですが、公式を暗記しただけでは、ほとんどの問題は解けません。また、解法を暗記したところで、そのままでは、どの問題にどの解法を適用すればよいかがわからないということもよくおこります。問題を解くためには、問題を変形したり分解したりして、既知のパターンに関連付けるという作業が必須です。つまり、機械的に暗記された断片的な知識ではなく、関連付けをしやすい状態にされている知識こそが、実際に問題を解く上では、役に立つのです。
さらに、知識を一方的に教え込むよりも、各人に自分なりの仕方で知識を関連付けさせた方が学習効果が高いということも示唆しているように思われます。バートレットは、無意味な記号列を実験材料にする従来の方法を批判し、内容に意味のある物語文を使った記憶実験を行いました。その画期的な実験によれば、被験者たちは、自分にとっては異質な内容や言葉を自分になじみのあるものに置き換えて記憶したそうです。
つまり、人は、自分が使える知識しか使うことができません。だとすれば、教えるのは応用範囲の広い最低限の知識だけにして、その知識の運用に各人なりに習熟させる方がよいということになります。使いこなせない知識をいっぱい抱え込んで、どれを使えばよいのかに頭を悩ますのではなく、使い勝手のよい知識だけを携えて、与えられた問題の誘導に身を任せながら、問題を解き進めていく訓練をすべきです。
1-3.成長は自然発生的なのか。
しかし、記憶と知識の関連付けの仕方を工夫しただけで学力が伸びるとは限らないように思われます。特に中学受験の場合、成熟度も学力に大きな影響を及ぼしていると考えられます。また、そもそも記憶と知識の関連付けの上手下手自体が成熟度に左右されるように見えます。したがって、もう一度議論を練り直す必要がありそうです。
子どもの学力の発達とは、大雑把に言うと、抽象力の発達だと言ってよいと思います。子どもは、およそ11歳から15歳までの間に、概念そのものを操作できる抽象力を身につけると言われています。文章を論理的に構成できるだけでなく、比といった抽象度の高い概念を理解できるようにもなります。こうした子どもの知力の発達には個人差があり、それが見かけの勉強量以上に学力の差を生み出していると考えられます。
ピアジェによる有名な実験を思い出してみましょう。長く細いコップ、普通のコップ、短くて太いコップはいずれも等量の液体を含んでいます。液体が等量であることを、3種類のコップの間で液体をやり取りすることによって、証明して見せます。液体は、形態は変えても、量は不変であるということを理解できない子どもは証明の手順も記憶できません。ところが、しばらくして再テストをすると、保存という抽象的な概念を理解できるようになった子どもは証明の手順をやすやすと記憶できるようになります。
では、知力はどのように発達し、学力差はいかにして生じるのでしょうか? 子どもは、ことばも話せない段階から広義の学習を始めます。たとえば、子どもは、失われたものを探すという行為を通してさえ、物の存在について学習しているのです。こうした無意識の学習の膨大な積み重ねによって子どもの知力は発達していきます。子どもの成長はほとんど自然発生的になされるように見えます。学力差が生じるのはほとんど偶然の結果であるように見えます。
1-4.教育を通して簡単に身につける。
では、子どもの自然発生的な成長に大人が意識的に介入することはできないのでしょうか? 子どもの成長は、生活環境の制約を受けながらも、十数年かけてほとんど偶然になされます。わずか数年の受験勉強の期間に大人がいくら干渉しても、その影響はごくわずかであるように思われます。結局、大人は、子どもの成長を待つしかないのでしょうか?
具体例から始めて、もう少し丁寧に議論し直してみましょう。たとえば、子どもは、大人に教えられていないにもかかわらず、日常の学習を通して、文法的に適格な文や論理的に正しい文章を話すことができるようになります。子どもは日常生活の中では有能な学び手です。ですが、限界はあります。日常会話を正しく行うことのできる子どもも、自分が使用した文法規則や論理関係を自覚的に説明したり、自分が使用した規則や関係を使って任意の文や文章を作ったりできるわけでは必ずしもありません。
低学年の小学生は「電車が遅れたので、遅刻しました」と言うことはできますが、多くの場合、「ので」ということばの働きをうまく説明できませんし、「ので」を使った任意の作文がうまくできません。日常生活の中で獲得された知識には応用力が欠如しています。
また、子どもは概念を経験的に獲得しますが、それを自覚的に説明できるとは限りませんし、そのため誤った概念を持ち続けることもあります。たとえば、子どもは「バラは花である」ことはわかっても、バラ以外に花があることを推論できない場合があります。
なぜ子どもは概念を自覚的に説明したり使用したりすることができないのでしょうか?
それは、経験的に獲得された概念がまだ体系化されていないからです。
たとえば、「花」という概念を正確に説明するためには、サクラ、バラ、チューリップなどが花であることを知っているだけでなく、実や種子などの生物学的な概念体系を獲得している必要もあります。概念の説明は、その概念を他の概念に関連付けることによってなされるほかありません。
また、たとえば、「ので」ということばを自在に操作するためには、「ので」が「つまり」、「しかし」、「そして」といかに違うかということを理解しておかなくてはなりません。
つまり、概念を説明したり使用したりするためには、概念の体系が形成されていなくてはならないのです。知識の応用ができるためには、概念が経験的に獲得されているだけでは不十分であり、それが体系化されていなくてはなりません。
概念はたんに現象の痩せ細った抽象なのではなく、体系化されることによって、現象をより豊かに具体的に表象するものです。
概念は、最初は、子どもが事物に直接触れるところからつくられます。初期の概念は経験的なものです。しかし、こうした経験的で貧弱な概念をもとに、概念の体系化が徐々になされていき、思考は具体的で豊かなものになっていきます。
だとすれば、子どもの学力の発達とは、概念の体系が形成されることによって、概念操作能力=抽象力が身につくことだと考えられます。そうした概念の体系は自然発生的に形成されますが、いわゆる「9歳の壁」が問題とされるように、日常の学習を通してだけでは十分に発達しない場合が多いように思われます。
つまり、「地頭のよさ」は、大抵の場合、教育なしで身につくわけではありませんし、少なくとも、教育を通してより簡単に身につきます。
ヴィゴツキーはかつて次のような実験を行いました。知能年齢が8歳の子どもに、8歳より上の年齢の子どものためのテストを与え、解答の過程でヒントを出してやります。すると、その子どもが自分の知能年齢より上の年齢の子どものための問題を解くことができるようになることがわかりました。
つまり、子どもたちは、他人の助けを借りれば、自分たちの年齢に許される以上の能力を発揮できるのです。そして、他人の助けがなくてはできなかったことをやがて自力でできるようになります。
1-5.成長と教育の間
子どもが自ら知識を体系化するのを助けるという教育は、従来「地頭を鍛える」とか「子どもを大人にする」とか言われてきたものとは異なります。それは教師による一方的な訓練=規律化ではありません。
概念の体系は経験的に獲得された概念をもとに形成されます。子どもが無意識に積み重ねてきた膨大な学習に依拠しない教育など不可能です。
また、すでに指摘したように、個々の子どもが各々のやり方で知識の体系化を図った方が学習効果が高いのです。教師は、子どもが自力でできるはずのことを実際に自力でできるように手助けするだけにすべきです。
実際、よく言われるように、もっとも学習効果が高いのは、まったく歯が立たない問題でも簡単すぎる問題でもなく、解ける時もあれば解けない時もある問題、あるいは解けそうで解けない問題、つまり解けるはずの問題に取り組ませることです。その場合、子どもが自力で問題を解けるようになるというのが目標となりますから、教師は、子どものやることをそっと見守るか、手をさしのべるにしても、最低限にとどめるべきでしょう。
子どもが自ら知識を体系化し、教師はそれを先導するにとどめる。それは、ルソーとロック以来、教育論争において永年繰り返されてきた、知識の詰め込みと子どもに合わせた教育という不毛な対立を回避して、成長と教育の間に留まることを意味します。
むろん、賢明にも中間に留まるのは安易に両極端に走るより困難です。それは、近代の教育が抱え込まざるを得なかった、成長と教育のパラドクスにあえて踏みとどまることで、その可能性の中心を切り開くことだからです。
ただ、それは英雄的な行為などではまったくなく、子育てをする親も含め、子どもを教育せんとする誰しもが日常的に体験しているものです。
普通、子どもは大人が思うように動いてくれません。
一を聞いて十を知ることのできる子どもや打てば響くような子どもはごく稀です。むしろ、指導実感からすれば、平均すると、十を教え込んで五くらいしか学んでくれません。
子どもの成長を真剣に望む教師はつねに教育の不可能性という壁にぶつかります。ですが、教師の思いとは無関係に、子どもは突然成長します。その成長の瞬間、長く続いたトンネルが不意に終わりを告げ、まばゆい陽光の射す出口が目の中の飛び込んでくるかのように、成長と教育のパラドクスは突如として雲散霧消します。
ただし、成長が教育の困難を解決したかに見えた、その瞬間、教師は再び教育の不可能性という奈落の底に突き落とされることになります。このドラマに終りはありません。
このようなありふれた成長/教育のドラマの中で、教師が教育の不可能性を痛感しながらも成長の可能性を信じることを続けることなくしては、子どもの成長/教育はあり得ません。
1-6.associationsというシステム
最後に、われわれが経験から自然に生み出したassociationsというシステムについて、以上のような原理的な問い返しを踏まえた上で、あらためて説明しておきましょう。
- 一方向的な集団授業でも子どもに合わせた個別指導でもない少人数制指導
- 大半の教科を継続的に指導することによって、個々の生徒の成長具合や個性を熟知し、いついかなることをいかにさせるのかを的確に判断できる教師
- 教師による説明ではなく、生徒による演習が主体であり、生徒が自分なりに知識の関連付けとその説明をできるように教師が先導する授業こそが子どもの学力を伸ばすのです。
それは、生徒と教師のassociations(関係の積み重ね)によって生徒がassociations(知識の関連付け)を行えるようにする、associations(関係の束)というシステムでこそ可能です。
2. 親の心構え
親が「勉強しなさい!」と言っても、たいていの子どもは勉強しません。勉強しないどころか、「勉強しなさい!」という親の言葉は、多くの場合、子どもの学習意欲をそぎます。子どもの成績が悪いことを親が叱るごとに、成績は確実に1点ずつ下がります。
成績のいい子どもの親の多くは、子どもを信じて、子どものすることを黙って見守ります。
子どもは次のような各段階での他者からの承認を通じて大人へと成長していきます。
- 親による、自己の存在の絶対的な承認
- 集団内での、自己の能力の相対的な承認
- 普遍的な理念にコミットメントすることによる社会的承認
子どもは、親が自己の存在を絶対的に肯定してくれるのだという安心感を得て初めて、集団内の厳しい競争へと自信を持って参加することができます。子どもに自信を失わせ、競争に参加する意欲を失わせることは親の役割ではありません。
とはいえ、見守るのは放置するのと同じことではありません。子どもの勉強のための環境づくりはして下さい。勉強のための環境づくりというのは、勉強道具を買い与えることではありません。子どもに勉強して当然だと思わせることです。
そして、そのためには、親の覚悟が必要です。勉強に関しては、甘やかしも同情も無用です。中学受験を選択した以上、子どもが勉強することは偉いことでも、かわいそうなことでもありません。受験をするのですから、勉強するのが当然です。勉強する子どもが偉いとかかわいそうだとかいう価値観は近代になってつくられたものでしかありません。
近代以前、子どもは労働力にすぎず、よその家で働かされることもまれではありませんでした。近代以前に帰れ、と言いたいわけではありませんが、愛情という親のエゴで、子どもの可能性にたがをはめてしまう必要はどこにもありません。
親がなすべきことを明確にするために、中学受験の目的を問い直してみましょう。中学受験の目的とは何でしょうか?
第一志望校に受かることでしょうか? 少しでも偏差値の高い学校に受かることでしょうか? しかし、残念ながら、勝負は水物ですから、必ずしも狙っている学校に受かるわけではありません。第一志望校あるいは偏差値の高い学校に受からなければ、受験は失敗だったのでしょうか?
そんなことはありません。第一志望校や偏差値の高い学校に受かっても、不満を抱く場合もあります。また、中学校に入ってからの成績が、第一志望校に入った子よりも第二志望校に入った子の方がいいという場合もあります。第一志望校や偏差値の高い学校への合格という目標の設定は必要ですが、目標を達成できたかどうかだけで中学受験の成否を決めることはできません。
では、どう考えればいいのでしょうか? そもそも、目的と目標は異なるものです。目的は目標の達成にだけではなく、過程そのものにもあると考えるべきです。たとえ第一志望校に受からなくても、中学受験を通じて子どもが成長をしたのを認めることができるのなら、中学受験はとりあえずは成功だったと言えるでしょう。ただ、それは第一志望校合格よりも困難なことです。
そもそも、受験勉強ができることや偏差値の高い学校に通うことは手放しで賞賛されることなのでしょうか?
受験勉強ができることや偏差値の高い学校に通うことの価値を否定するつもりはまったくありません。しかし、少なくとも、受験勉強ができることと知性とは何の関係もない、とは言えるでしょう。知の起源にまで遡って考えると、ソクラテスが言うように、知性とは、定義上、おのれが無知であることを知ること以外のものではありません。つまり、知識があり、受験勉強ができるから知的なわけでは全くないのです。
人間の粗い頭脳ではとらえることのできない世界の深みに謙虚に怖れを抱き、世界の豊かさをそのまま肯定することこそが知的な振る舞いです。おのれの性能の悪い頭脳で世界の秘密をつかんでいると思いあがっている「センセイ」よりも、自然の素材を生かすために謙虚に自らの技を磨く名もなき職人の方がよほど知的です。
自己を売り込むことしかしない前者より、後者の方がよほど普遍的な仕事をしていて、社会の役に立っています。そして、普遍的な仕事をし、社会の役に立つには、時間が必要です。職人が一人前になるためには、何十年とかかるように。中学受験は、おのれの無知に気づき、世界へとおのれを開いていくという長い成長の一過程でしかありません。
私たちが目指すのは、たんに知識を授けることではありません。自ら成長する意志を持つ人間を育てることです。中学受験は子どもの成長のための絶好の機会となり得ます。
親がやるべきなのは、そうした子どもの成長を助けること以外にありません。やるべきことを真っ当にやっていれば、結果は自然とついてきます。
3. 入試概況(2023年)
2023年2月1日午前に首都圏(1都3県)の私立中学校を受験したのは43,000人あまりでした。ボトムであった2015年の約36,000人から7,000人ほど増え、中学受験バブルと言われた時代のピークであった2007年の約44,000人に迫っています。
受験者数の増減の短期的・中期的な原因は小学生数の増減、景気、大学受験の難化、公立不信にあると考えられます。
小学生数の増減から見ていきましょう。全国的な少子化の傾向に反し、ここ数年ほど、受験率の高い東京都の小学生数が増加傾向にあります。ただ、小学生数の増加より受験率の増加の方が受験者数への影響は大きいと言えます。実際、過去の中学受験バブル期(1990年前後とゼロ年代)は東京都の小学生数が減っていた時代でした。
次に、景気です。たしかに、バブル崩壊後の1990年代後半とリーマンショック後の2010年代前半は、概して受験率は下降気味でした。しかし、現在、景気はちょうど曲がり角に立っているところですし、受験勉強を始めてから実際に受験するまでには3年ほどかかりますので、景気の受験率への反映にはタイムラグがあるのが普通です。景気の影響が出るとしても、しばらく先のことでしょう。
続いて、大学受験の影響を見てみましょう。中学受験バブル期と重なる1986年から1992年は、大学受験関係者にとっては「ゴールデンセブン」と呼ばれる時代でした。第二次ベービーブーマーが大学受験期を迎え、定員の倍ほどの数の受験生が殺到して、受験生の半数あまりしか大学に入ることができないというほど、大学受験が難化した時代だったのです。今回の中学受験者数の増加の当初の原因も、大学入学共通テストの負担増と入学定員の厳格化によるいわゆる早慶マーチなどの私立大学の難化にあったと考えられます。実際、中学受験者数の増加を牽引したのは当初は付属校人気でした。大学付属校に入学すれば、大学入学共通テストや私立大学の一般入試を避けることができるというわけです。なお、私立大学の入学定員の厳格化は緩和の方向に向かっていますが、大学入学共通テストの負担は増す方向にあります。難関化した早慶マーチが大きく易化することはないでしょう。
最後に、公立不信です。私立校が台頭したそもそもの原因は、自治体が導入した学校群制度(学校間格差をなくすために、受験者本人の希望にかかわらず合格者を学校群内各校に割り振る制度)でした。数十年にわたる中学受験ブームの根底には、1980年代に社会問題となった校内暴力やゼロ年代に塾がしきりに煽った「ゆとり教育」への不安などの公立不信があると考えられます。今回も、コロナ禍での公立中学校のオンライン対応の遅れが連日のように報道されたことが、私立中学校の受験者数の増加の原因だと思われます。
ともあれ、私立中学校の受験は、受験者数の回復に伴い、全体的な競争の激化が見られます。一足先に人気が回復していた大学付属校は人気高止まりの様相を見せ、付属校や共学校と比べ、比較的受験が楽だった中堅進学校の男子校・女子校の入試も厳しいものとなっています。今後もしばらくは厳しい受験が続きそうです。一部では「付属校離れ」や「今年がピーク」といった意見も見られますが、楽観的な見通しは慎むべきでしょう。